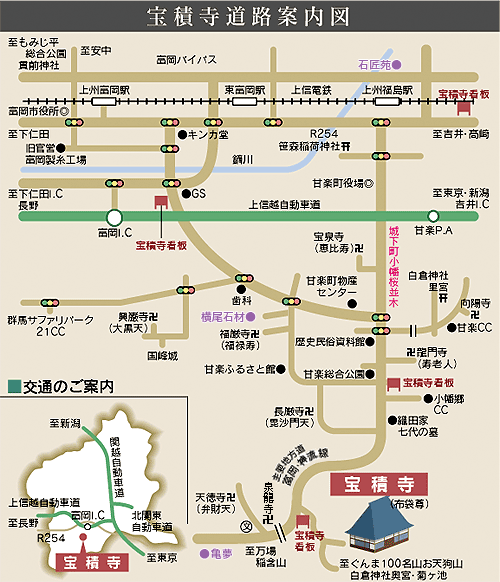| トップページ | 宝積寺のご紹介 | お寺の年中行事 | お寺の楽しみ方 | ボランティアについて | 霊園情報 | リンク |
|
宝積寺(ほうしゃくじ)は、現在のお寺より南に4キロ行った山の中腹にある天寿庵(てんじゅあん)と言う庵(いおり)からきています。 お寺の境内には、弘安3年(1280年)、正安4年(1302年)、延慶2年(1309年)の板碑が建立されています。この時代にはすでに天台宗の寺として、広い寺領を持ち、栄えていました。 そして、宝徳2年(1450年)に、領主の小幡実高候(おばたさねたか)が中興開基となり、茨城県東昌寺の即庵宗覚禅師を請いて曹洞宗(そうとうしゅう)として再興されました。 曹洞宗については、こちらに詳しく書かれてあります。 小幡氏が滅ぶと、元和2年(1616年)に織田信長の孫・織田信良候が小幡藩の藩主となり、菩提寺を宝積寺と定め、毎月参詣されました。 寛政5年(1793年)31世孤燈独明大和尚(ことうどくみょうだいおしょう)が再建されたのが、写真にもございます現在の本堂です。 宝積寺は近年まで修行道場として栄えました。特に27世万仭道坦禅師(ばんじんどうたんぜんじ)が住職として入山すると、全国から多くの修行僧が集まるようになり、禅風大いに振るい、永平寺・總持寺の両本山へも多くの禅師が昇住しています。 |
 万仭道坦禅師 (ばんじんどうたんぜんじ) |
|||||
|
平成5年に菊女伝説の主人お菊様の観音像が建立され、翌年その精神を生かした取り組みとして「かんのんボランティア会」が発足しました。カンボジアの子供たちへ、 小学校校舎(4校舎)、絵本(約4千冊)を贈る運動などを行っています。 また、国内では東日本大震災支援で岩手県陸前高田市仮設住宅40戸への日用品(お米・タオル・下着など)の支援を現在も行っています。 また、小幡七福神、新上州観音霊場、東国花の寺百ヶ寺の札所巡り、写仏教室、坐禅会には多くの方々が集われています。 これらの催しは他のページに詳しくご紹介していますので、そちらをご覧下さい。 |
 菊女観音 |
|||||
|
お寺では、檀家様だけでなく多くの方々に訪れて頂きたいと思っております。 春には樹齢150年のしだれ桜が、梅雨の時期にはしっとりと紫陽花が咲きます。お盆には万燈会といって、竹の中にロウソクを入れた灯籠2000本、行灯200灯、ガラス灯籠500灯、プラスチック灯籠1500灯で境内を飾る催しを行います。そして、秋には黄金色に輝く大いちょう。晩冬には蝋梅(ろうばい)が咲き誇ります。 四季折々にお楽しみ頂ける宝積寺に、是非お越し下さい。
|
||||||
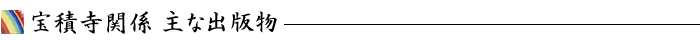
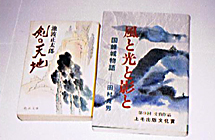 |
 |
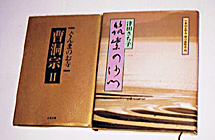 |
|---|---|---|
| ○1979年8月25日 「剣の天地」 池波正太郎 新潮社 \520 ○1989年8月1日 「風と光と影と」 田村貞男 上毛新聞社出版局 \1,630 ○1996年7月30日 「検証 四谷怪談 血屋敷」 永久保貴一 朝日ソノラマ \880 |
○2001年9月19日 「鷲  山宝積寺史」 宝積寺史編集委員会 宝積寺(残少なし) 山宝積寺史」 宝積寺史編集委員会 宝積寺(残少なし)※宝積寺 曹洞宗開創550年を記念とし、平成13年に発刊。 |
○2003年1月25日 「ぐんまのお寺曹洞宗2」上毛新聞社 \1,470 ○1981年12月1日 「筑紫の沙門」 津田さち子 大本山永平寺祖山傘松会 \2,300 |
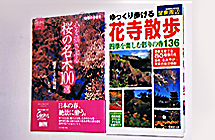 |
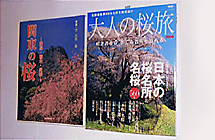 |
 |
| ○2007年3月16日 「心を揺さぶる桜の名木100選」大貫茂 ダイアモンド・ビック社 \1,470 ○2007年4月1日 「花寺散歩」成美堂出版 \1,155 |
○2008年2月28日 「関東の桜一群馬・栃木・茨城」小林隆 歴史春秋出版 \2,100 ○2008年3月23日 「大人の桜旅2008」ニューズ版 \1,260 |
○2008年春 「Ways」JAF MATE \1,700 ※「Ways」で全国の一本桜の名木として紹介される。 |
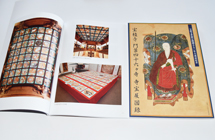 |
||
| ○2017年7月 「宝積寺門葉46ヶ寺 寺宝展図録」同編集委員会編集 宝積寺発行 ※宝積寺曹洞宗開創570年大遠忌記念として平成29年発行 |
※宝積寺以外の出版物は、書店等でお買い求め下さい。